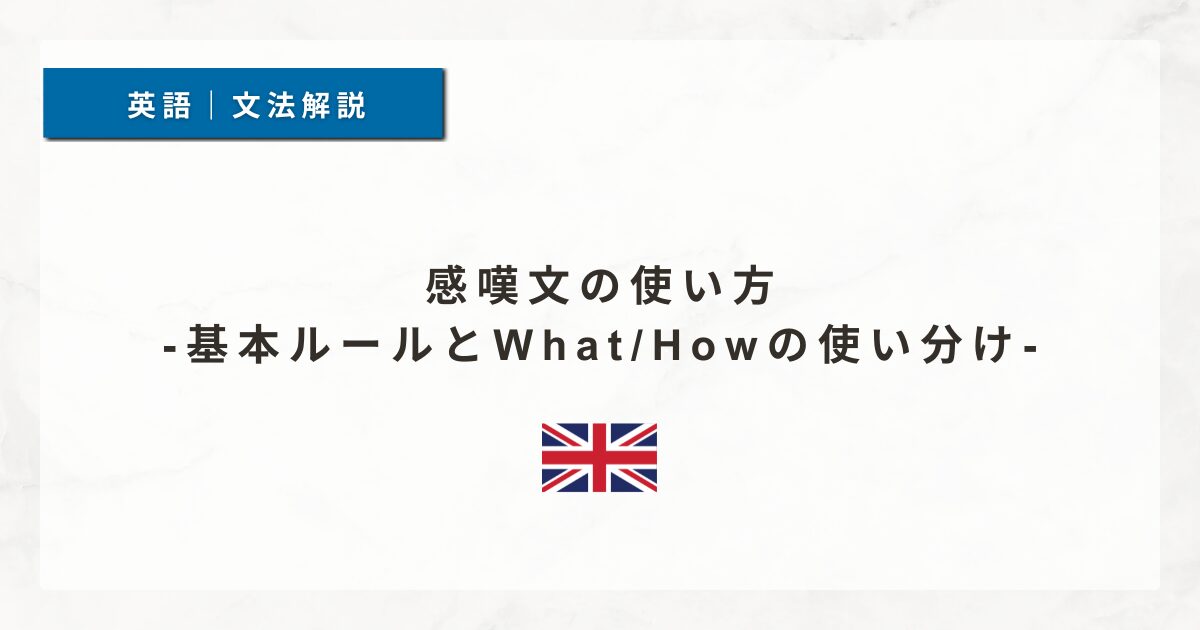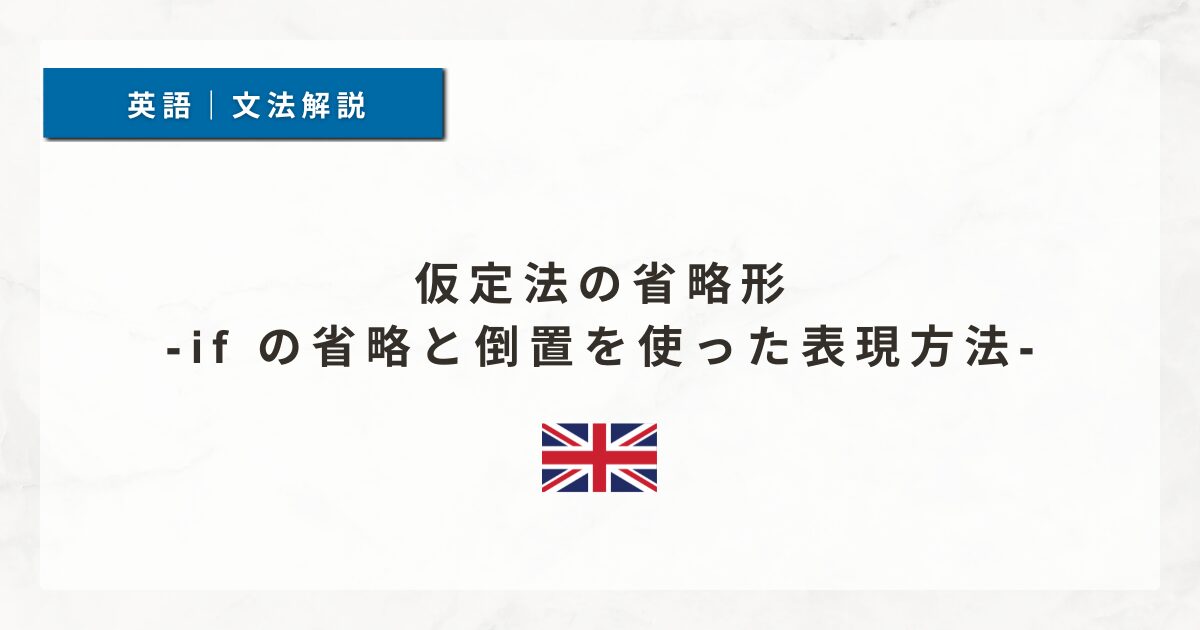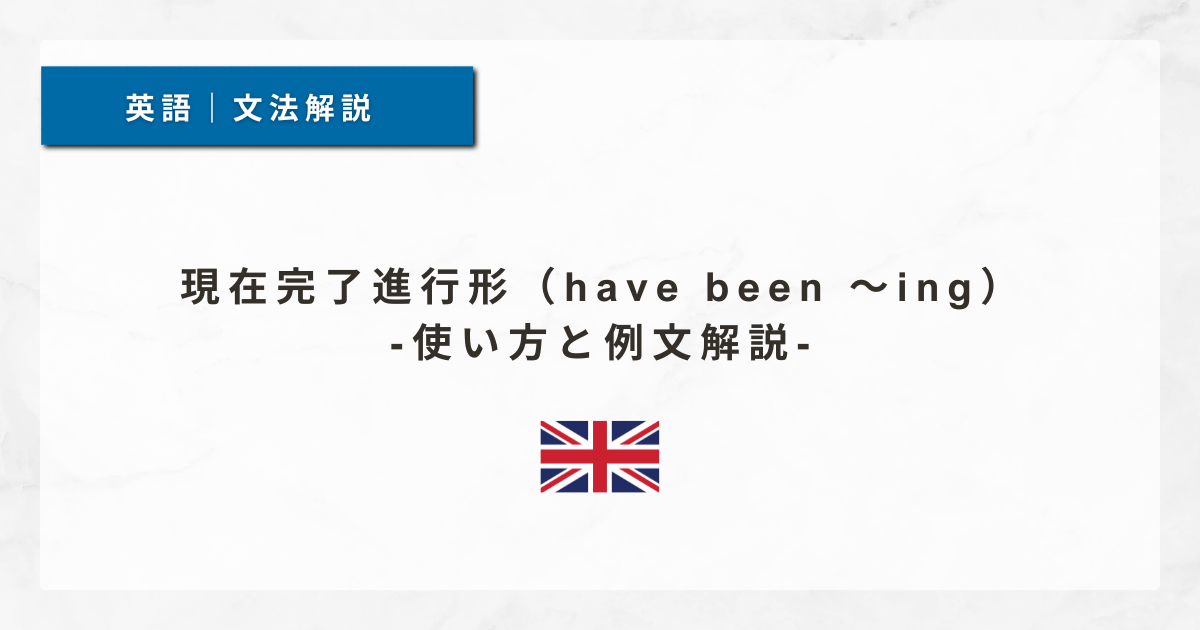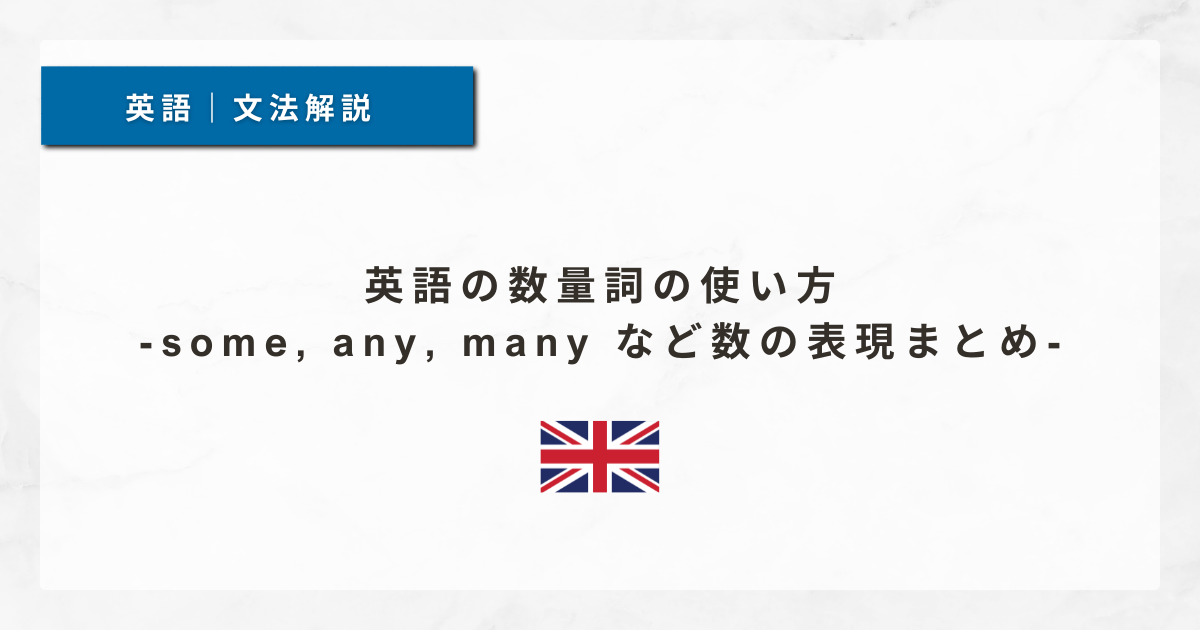#1 英語の語順と5文型|基本ルールと例文解説

英語では、語順は文の意味を決める大切な要素です。
日本語では「私はリンゴを食べる」「リンゴを私は食べる」のように、語順をある程度自由に変えられますが、英語では語順を間違えると意味が通じなくなります。
今回は、英語の語順の基本である5つの文型(SV/SVO/SVC/SVOO/SVOC) を紹介し、それぞれの使い方を例文とともに解説します。
1. 英語の語順と5文型の基本ルール
英語は「語順」が重要な意味を持つ言語です。語順が崩れると文の意味そのものが伝わらなくなるほどで、「英語の語順=文の骨組み」とも言えます。
英語の語順は、基本的に「主語 → 動詞 → その他の要素」の順に並びます。これは英語にとって非常に強いルールで、例外はほとんどありません。
この語順ルールをもとに、英語の文は主に次の5つの文型に分類されます。
| 文型 | 構成 | 例文 | 文の意味 |
|---|---|---|---|
| 第1文型(SV) | 主語+動詞 | She sleeps. | 彼女は眠る。 |
| 第2文型(SVC) | 主語+動詞+補語 | He is a doctor. | 彼は医者だ。 |
| 第3文型(SVO) | 主語+動詞+目的語 | I play tennis. | 私はテニスをする。 |
| 第4文型(SVOO) | 主語+動詞+間接目的語+直接目的語 | She gave me a gift. | 彼女は私にプレゼントをくれた。 |
| 第5文型(SVOC) | 主語+動詞+目的語+補語 | They call him Tom. | 彼らは彼をトムと呼ぶ。 |
補語(Complement)とは、主語や目的語の「説明」や「状態」を補足する語句のことです。補語には名詞、もしくは形容詞が使われます。
- He is tired.(補語=tired)
be動詞や become, seem などを使って主語の性質や状態を説明し、主語と補語は「=」の関係になるのが特徴です。
2. 各文型のポイント解説
2-1. 第1文型(SV):主語+動詞だけで意味が伝わる最小構文
第1文型(SV)は、「主語(S)+動詞(V)」の2つだけで文が成り立つ構造です。動詞が「自動詞」で、後ろに目的語を取らない場合に使われます。
- The baby cried.
(赤ちゃんが泣いた) - He sleeps.
(彼は寝る)
この文型は、主語と動詞だけで完結するため、英語の最小単位の文といえます。
また、自動詞のあとには副詞句や前置詞句(in the morning / at the stationなど)を加えて意味を広げるのが一般的です。
2-2. 第2文型(SVC):主語と補語が「=」の関係
第2文型(SVC)は、「主語(S)+動詞(V)+補語(C)」という構成で、主語の性質・状態・身分などを補語で説明します。
be動詞(am, is, are)や、become, seem などの「状態を表す動詞」が使われます。
- He is a teacher.
(彼は教師です) - The soup smells good.
(スープは良い匂いがする)
第2文型(SVC)の「C」にあたる補語には、名詞もしくは形容詞が使われます。
- 名詞:身分・職業など(a student, a doctor)
- 形容詞:状態・性質(happy, tired, angry)
「主語=補語」の関係になることを意識することで、文の意味がわかりやすくなります。
2-3. 第3文型(SVO):主語+他動詞+目的語の最も基本的な語順
第3文型(SVO)は、英語で最も頻繁に使われる構文です。主語の「行動」によって何かしらの「対象(目的語)」が関係する文になります。
- She likes music.
(彼女は音楽が好き) - I read a book.
(私は本を読む)
ここでの music や a book が目的語(O)です。動詞 like や read は他動詞であり、目的語なしでは意味が成立しないので注意しましょう。
2-4. 第4文型(SVOO):「人」に「物」を与える構文
第4文型(SVOO)は、動詞が「間接目的語(人)」と「直接目的語(物)」の両方を取るときに使われます。give, send, tell, teach などの動詞が典型的です。
- She gave me a book.
(彼女は私に本をくれた) - He told us a story.
(彼は私たちに話をしてくれた)
上記の例文では、「me」「us」が間接目的語、「a book」「a story」が直接目的語です。
各目的語の順番は、人(間接目的語)→ 物(直接目的語)が基本となります。
ただし、同じ意味でも、「物+to+人」の形に言い換えることも可能です(例:He sent a message to me.)
2-5. 第5文型(SVOC):目的語の「状態」を補語で表す
第5文型(SVOC)は、動詞が目的語と補語の両方をとり、目的語がどうなったか・どうであるかを補語が説明する構文です。
- We made him angry.
(私たちは彼を怒らせた)
上の例文では「him」が目的語、「angry」がその状態を表す補語です。つまり、動詞と目的語の間に「何が起きたか」「どんな結果になったか」という関係性を示すのが第5文型の特徴です。
第5文型に使われる動詞は限られており、make, name, call, find, keep, consider などがよく登場します。
3. まとめ
- 英語では、語順が意味を決定する。
- 英語の文は「5文型」に分類されることで、文の構造が明確になる。
- SV(第1文型):自動詞のみで文が成り立つ。
- SVC(第2文型):主語を補語で説明。「=」の関係。
- SVO(第3文型):他動詞と目的語を使う最も基本的な文型。
- SVOO(第4文型):「人に物を与える」といった動詞で2つの目的語を取る。
- SVOC(第5文型):目的語の状態や呼び名を補語で表現する構文。